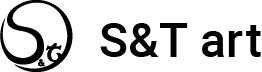ちょっとしたミステリー
こんにちは、S&Tの上村です。昨日、高畠駅の前の歩道を歩いていると不思議なものを見つけました。それがこちら ⬇︎

歩道はずっと周りのレンガのような石畳になっているのですが、その中に一つだけこんなものが。
なんだろうと思って真ん中のDennis Ruabonという文字を調べてみるとイギリスのウエールズ地方のルアボンというタイルの名産地のものでした。なんでそんなものが???
発見してから気になって、ずっと下向いて歩いていましたがこれ1個だけでした。
なぜ1個だけ???
と疑問に思いながら調べてみましたが、それ以上のことは全く分からず。
嫁とあーでもないこーでもないと議論しながら、身近にあるちょっとしたミステリーを楽しんじゃいました。(笑)
誰かご存知の方はぜひS&Tへ来て教えて下さいね。😆
タイルで思い出したのが先日ペンギン文庫さんで買った岡﨑乾二郎さんの画集。サイン入りだった貴重な作品集だけにそっと開いてじっくり見ていなかったので、せっかく思い出したのでもう一度隅々まで見てみようと思いました。(笑)
岡﨑乾二郎さんと言えば今年の7月まで東京都現代美術館で展覧会が開催されていたのでご覧になった方も多いことでしょう。ちょっとだけおさらいしておきますか。
まずはプロフィールから。
岡﨑乾二郎(おかざき・けんじろう)
造形作家、批評家。
1955年東京生まれ。1982年パリ・ビエンナーレ招聘以来、数多くの国際展に出品。総合地域づくりプロジェクト「灰塚アースワーク・プロジェクト」の企画制作、「なかつくに公園」(広島県庄原市)等のランドスケープデザイン、「ヴェネツィア・ビエンナーレ第8回建築展」(日本館ディレクター)、現代舞踊家トリシャ・ブラウンとのコラボレーションなど、つねに先鋭的な芸術活動を展開してきた。東京都現代美術館(2009~2010年)における特集展示では、1980年代の立体作品から最新の絵画まで俯瞰。2014年のBankART1929「かたちの発語展」では、彫刻やタイルを中心に最新作を発表した。長年教育活動にも取り組んでおり、芸術の学校である四谷アート・ステュディウム(2002~2014年)を創設、ディレクターを務めた。2017年には豊田市美術館にて開催された『抽象の力―現実(concrete)展開する、抽象芸術の系譜』展の企画制作を行い、2019〜20年には同美術館で大規模な個展「視覚のカイソウ」が開催された。
主著に『而今而後 批評のあとさき(岡﨑乾二郎批評選集 vol.2)』(亜紀書房 2024年)、『頭のうえを何かが』(ナナロク社 2023年)、『絵画の素 TOPICA PICTUS』(岩波書店 2022年)、『感覚のエデン(岡﨑乾二郎批評選集 vol.1)』(亜紀書房 2021年)、『抽象の力 近代芸術の解析』(亜紀書房 2018年)、『ルネサンス 経験の条件』(文春学藝ライブラリー、文藝春秋 2014年)、『芸術の設計―見る/作ることのアプリケーション』(フィルムアート社 2007年)。『ぽぱーぺ ぽぴぱっぷ』(絵本、谷川俊太郎との共著、クレヨンハウス 2004年)。作品集に『TOPICA PICTUS』(urizen 2020年)、『視覚のカイソウ』(ナナロク社 2020年)。
『感覚のエデン(岡﨑乾二郎批評選集 vol.1)』にて2022年、第76回毎日出版文化賞(文化・芸術部門)受賞。『抽象の力 近代芸術の解析』にて、2018年、平成30年度(第69回)芸術選奨文部科学大臣賞(評論等部門)受賞。

Spread legs. Never to perish again. Only a presence – the subtle movement of air as someone searched. Solely ephemeral presence lingers. I remember who I am. Earthquake shook. Sun black as sackcloth. Moon like blood. Stars fell to earth, fig tree dropping unripe fruit. Sky split apart, mountains and islands moved. Kings, slaves shouted, “Hide us from the throne, from the Lamb’s wrath.” Their day has come. I’m gonna faint!”
2024年
アクリル、カンヴァス
260.6×268.2 cm
タイトル長いですよね😅

右『自分の暮らした村がこんなに小さく思われたことはない。太陽が姿をみせた。背の高いポプラの林は風に吹き動かされる砂浜のような格好をしている。切れ目のないその連続を見ているだけで眼がくらんでくる。変り映えしない日々の連続に酔うことができたなら象や蛇をしとめた気にもなれる。蝶が舞うようにそんな風に彼はものを識ったのである。』
2002年
アクリル、カンヴァス
各180.0×130.0 cm(2点1組)
こちらのタイトルもまるで詩です。
AIをはじめとする科学技術の革新、環境危機、政治状況の混沌により、私たちが捉えてきた世界や社会を制御してきた制度は急速に失効しつつあるように思える昨今。
『世界は崩壊しつつあるのか?』という疑問に対し岡崎さんはこう答えています。
「世界は崩壊しているのではない。動揺しているのは私たちの認識である。『造形』とは、私たちが世界を捉える、その認識の枠組み自体を作り変える力です。すなわち、認識を作りかえることで世界の可塑性を解放し、世界との具体的な関わりを通して認識の可塑性を取り戻すことです。『造形』とは、この二つの可塑性を実践的に繋ぎなおすことだ。」と。
展覧会のタイトル『而今而後 ジコンジゴ Time Unfolding Here』も論語の一節から取られたそうですよ。
岡崎さんも御年70歳。まだまだこれから活躍してくれそうです。
道端のレンガからこんな事まで考えながら歩いていたら今日は筋肉痛です。(笑)
それでは皆さん本日も良い1日を。