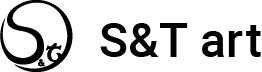言霊?
こんにちは、S&Tの上村です。昨日ブログで書いたからなのか、やはり事件は起きました。言霊でしょうかね😅
同会場の作家が1人高熱を出したりと一体どうなることやらと不安なことばかりです。その他にも色々ありました。(笑)
穴埋めなどなんとか対策は考えるものの、結局のところ本日現場に行ってみないとわかりません。今日は一体いつ帰れるんだろうと今からブルーです。😓
皆さんの笑顔だけを考えて頑張ろうと思います。まだ始まってもいませんが…(苦笑)
さて、つい先日、贋作を持つ美術館で脚光を浴びた高知県立美術館がまた物議を醸していますね。
ことの発端は高知県が同美術館を含む5つの県立文化施設について、管理者を直接指名する「直指定」から民間事業者を含む公募にする方針を打ち出したためです。
県は自主事業の拡大による収益増を目指し職員の待遇改善につなげたいとしていますが、対象施設や識者から事業や雇用の継続性を不安視する声が続出。7~8月に実施された県パブリックコメントには県内外から約300の団体や個人が意見を寄せ、波紋が広がっているというわけです。😅
この問題を聞いた時いかにもお役所仕事らしい発想だなと思い、昨年の『辺藝』開催時の県の対応を思い出しちょっとイラッとしました。
これに対しての高知県立美術館の館長のコメントも掲載しておきますね。
『県から県文化財団に指定管理者を公募にする方向性が伝えられたのは方針を変更した少し前で、急な方針転換に財団も館職員も困惑しています。県立美術館と坂本龍馬記念館は、いずれも比較的予算規模が大きく、入場者数もある程度確保できるので、県側は『もっと稼げるのでは』と考えたのかもしれませんが、そもそも美術館は収益目的の施設ではありません。国際組織のICOM(国際博物館会議)の定義でも、ミュージアムは『社会のための非営利の常設機関』と位置付けられています。美術館や博物館はどこも基本的に財政は厳しいですが、当館も管理代行料以外に助成金を最大限活用し寄付金を集め、可能な限り経費削減にも努めて運営が成り立っています。公募を導入しても収益増は現実的でないと考えます。文化遺産を次世代に伝える役割を担う美術館は、運営に長期的な継続性が必要で、原則5年で管理者が変わり得る公募制はその妨げになりかねません。公募の導入は、学芸員らの雇用不安を招き、離職につながる恐れがあり、優秀な人材が集まりにくくなります。』
結局のところ、何も分からない県知事や公務員が『あーでもないこーでもない』と考えて、実態にそぐわないアイディアを出してきます。専門家には相談せずに決定するからこうなるんでしょうね。
なんで公務員ってこうなんでしょうね?
首を傾げちゃいます。
そして強い決定権を持っているのは何も分からない素人の公務員。
だから揉め事が絶えないんでしょうね。
こういうことを言うとまた怒られそうですが、あくまで私見です。
問題は違えど昨年の『辺藝』の時は、せっかくフックもある駅の連絡通路を使わせて欲しいとお願いしただけなのに貸してくれなかったのですが、その理由が酷かった。
『公共の場所なので公共の団体にしか貸せない』というもっともらしい理由をつけて断るのに1ヶ月後に連絡してきましたよ。😅
何も販売しようとかしているわけでもなく危険でもない展示がしたいだけだったのにそれは酷すぎる。大体公共の団体ってなんだと思いました。そもそもそれだけの返事をするのになんで1ヶ月もかかるんだ?
ちなみに、その駅の連絡通路の壁面はいまだに何も使っていません。
全くの無駄ですよね。貸せないなら税金返せ💢
思い出してまたイラッとしちゃいました。(笑)
今回の高知県立美術館の問題は全てが館長の意見に賛成というわけではありませんが、頑張って欲しいなと思います。
今回は美術館の問題ですが、公務員や政治家の浮世離れした発想っていろんなところで見かけますよね。発想だけならいいんですが、実害があるのが困ります。
この機会に皆さんもこういう問題をちょっと考えてみて下さい。
ちょっと熱くなってきたので今日はここまで。
続きは会った時にでもしましょうね。
それでは皆さん本日も良い1日を。